|
|
|
|
スエヒロ 極妙 #15000・#20000
|
|
|
|
個人的に気になっていたが、高価な為に購入は躊躇していた砥石です。 今回ブログで知り合った友人の『酪農家』さんからお借りできたのでレポートする事が出来ました。 紹介用の砥石全体の撮影を忘れまして、上の画像はメーカーの販売サイトから拝借しました。 #15000はもう少し濃く鮮やかなグリーン色です。 スエヒロのフラッグシップともいえるシリーズのようで、価格もフラッグシップと呼ぶにふさわしい価格帯ですが、価格に見合うだけのコストもかかっているようにも思われる。 凍結までは分からないが、通常の温度変化や水に付けておく事での軟化やひび割れなどの変質に強いらしく、メーカーもその部分に自信を覗かせており、また研ぎ味にも自信ありのようである。 #10000・#15000・#20000の三つのバリエーションで構成されている。 説明書によると研磨材は#13,000(1ミクロン)から#20,000(0.5ミクロン)まで粒子を擦りあげているらしい。 |
||
| 使用感について |
||
まず、数値にも表した通り人造としては群を抜いて硬い砥石である。 価格だけ見ると人造としては高価ですが、摩耗が非常に少なく研ぎ感も上々の砥石です。 天然のとんでも無い硬さの砥石とまではいかないまでも、天然の超硬口の域の砥石と同等の硬さがあるようにも感じますが、減らない理由は他にもありそうです。 説明では無機質焼成品粘土とあり、研磨剤はホワイトアランダムとグリーンカーボランダムとある。 いわゆるWAとGCと呼ばれる呼ばれる研磨剤を配合し炉で焼いて造ってあるという事らしい。 ただ、不思議かつ妙な感触のある砥石でその辺りがメーカーの秘密なのかもしれない。 この不思議な感触は砥面の修正からも感じ取る事が出来る。 下りの数値は低めですが、これは僕がなるべく刃と砥面と合うようにベタ研ぎした事と、砥面を充分にツルツルに均して研いだ数値の為で、 砥面の荒れ具合により食いつきの感触や下りの感触など大きく異なる。 研磨剤も多そうですし実際はもっと下りると感じる方が多いのではないかと思います。 ある程度刃物を面で捉えると軽快ですが、場合によってはツッパリ感が出る場合もある。 線や点で捉えると食いついている感がありますが、研ぎにくいと感じる種類の重さはない。 非常にまじめに研究されて出来た砥石である事を感じさせます. 吸水量で砥面が少し反ったり凹んだりがあるようですが、特に問題を感じない方が殆どではないかと思います。 いろいろな面が混在している砥石で、お借りしている間にいろいろと検証してみようと思います。 |
||
まずお借りした砥石の砥面修正から始める。 定規で確かめたところ丈方向に中央が凹み、幅方向には中央が高いようである。 いつものようにアトマエコノミー粗目#140で修正をはじめるが、あらかじめ硬くて修正が嫌になると聞いていたので、いつもの手順の応用で全体に満遍なく落としていくのではなく、減らすと安定しやすい部分を狙って部分的に減らしてから、全体をつかって擦るを繰り返して平面を出していくが、確かに思うようには減らない。 それでも繰り返していくと何とか減ってきたようである。 仕上げ砥石なのでここで中目#400のアトマにチェンジして砥面の表面を均す。 こちらは砥泥も殆ど出ず下りない。 おかしい、ダイヤより硬いはずはないのである。 それどころか妙にビニールチックな輝きさえ出てくる。 しかし平面精度に感触的に違和感を感じるので却下。 |
||
 |
||
おおよそこういう石は普通に#1000あたりの人造砥石で共擦りして仕上げるのが妥当である事が多く、試してみると正解だった様子。 基本的には黒幕#1000で擦り合わせてから砥泥をそのまま置いておき、砥面の崩れが少ない事が予想されるケント硬口で仕上げに平面精度を出す。 |
||
 |
||
いざ試し研ぎ用の鑿を研いでみるとよく下りるが、通常は砥面を修正した直後は砥面表面が荒れているので下りやすいものである。 いつものようにしばらく砥面全体をくまなく使って研いでみるが、砥石が減りにくい事が災いして砥面の荒れがなかなか均される様子がない。 研いだ鑿の刃の表情を見ても白い傷が目立つ。 普通の仕上げ砥石は通常#1000で共摺りしたら充分で、すぐに落ち着くのだがそうはいかないようだ。 |
||
 |
||
| 仕方がないのでキングS-1やG-1といった仕上げ砥石で擦り直して研いでみるが、なおも荒れている。 更にエビスーパー#10000も試したが、いずれも食いつきよく下りも良いが極妙の高番手に見合った研ぎあがりには、なかなか行き着きそうにない。 不明のアルミナ研磨剤(#8000ぐらいなのだろうか?)を振りかけて硬い天然砥石で擦り合せると、ようやくぼやけたような蛍光灯の光が映る。 極妙の#15000と#20000を共摺りすると良いかと擦り合せてみるが、真ん中だけが鏡面のようになったので、水分を拭き取って精密定規で見ると真ん中が高い。 #1000の段階では平面調整はバッチリにしておいたが、全体が分厚いゴム製の砥石台なので、前後の圧がかかった方に沈み込む影響で前後がたくさん減ってしまったかと最初の段階では思ったが、どうやら#1000以降の修正で砥面が更に水分を吸収して表面が全体に膨張し盛り上がってしまったらしい。 使用前の殆ど吸水していない状態で#1000で平面に修正した為に、それ以降の仕上げ砥石で砥面修正が進行するにつれ吸水が進んでしまって盛り上がってしまったのだろう。 膨張については後ほど触れるとして、砥面がぼやけて光るぐらいまで滑らかにした砥石で研ぎはじめると下りは強めの感じだが、本来は支障をきたすまで砥面修正をせず連続使用していると、砥面表面の荒れはなくなるであろう事から、なるべく近い状態まで滑らかになるまで多少時間がかかるが、砥面全体を使って研ぐ。 ようやくある程度滑らかになると真上にある蛍光灯が映り込むようになる。 この時点で、なるべく刃と砥面の接地面積を多くして面で研ごうとすると砥面修正での砥面の小さい凹凸が無くなり、下りはかなり弱くなっている。 |
||
 これぐらい光る所まで実際に研いで砥面を滑らかにする。 |
||
なぜこのような事をするかというと、細かい粒度の砥石の本当の能力を知る為である。 例えば平面に細かい研磨剤が付いている場合は、刃には研磨剤なりの凹凸が付くだけだが、それに比べ砥面を直し表面が荒れた状態がのこぎりの刃のような状態だとして、鋸の刃の一つ一つにさらに研磨剤が付いているとしたら、刃の研磨痕は高低差の大きな凹凸になりより深い傷が刃に付きやすくなるのではないか? 普通はちょっと研げばすぐに滑らかになるのであるが、この砥石は極端に減らないので少しの事がなかなか滑らかにならず、充分に下準備する事となったのである。 |
||
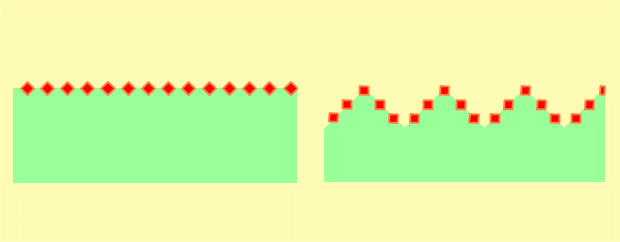 グリーンが砥面で赤が研磨剤のイメージ |
||
人造である程度の硬さがあり高番手の砥石の場合、砥面から剥がれ落ちた粒子(遊離砥粒)を嫌う事も少なくないと感じます。 実際に研いでみると砥面をツルツルにして、最終的な仕上げは頻繁に水で砥面と刃の間に砥泥や鉄粉が挟まって悪さをしないように掃除して、砥泥ではなくほぼ透明な水の状態で表裏何度か研いだ方が鋭利な刃が付くようである。 遊離砥粒が無い状態では研磨剤が埋まった状態なのに対し、遊離砥粒があると研磨剤がまるっきり砥面上に飛び出した状態なので、深い傷が入ったり砥面までの凹凸差が大きくなるのかもしれない。 あくまで仮説ですが。 遊離砥粒を減らす為にたびたび洗いながら刃先が確実に研げるように意識して、同時に刃先から遠く側も捉えてなるべく面で研ぎ、力は刃先を確実に捉えようと入れすぎず、グラグラしないように抜きすぎずで研いだのが下の画像です。 以前と撮影方法を変えたので刃先付近しかピントが合いませんが、今まで捉えられなかった研ぎ傷なども写るようになり、傷の深さなども少しイメージしやすくなった気がします。 包丁などで糸小刃を浸ける場合は、面積あたりの圧力が高くなるのでもう少し深い研ぎ傷になると思います。 刃先の黒いのはたぶん使用した刃の問題だと思われます。 なお天然砥石で仕上げた刃先については、撮影法を試し撮りした時のPC内にあった画像を利用しただけですので、あくまで平均的な仕上がり程度とお考えください。 |
||
|
||
| 次のページ> | ||