現状 205(長さ)×75(幅)×29(厚み) |
| 別誂え(べつあつらえ) |
| 高原料比率人造砥石 #1000 硬口 |
現状 205(長さ)×75(幅)×29(厚み) |
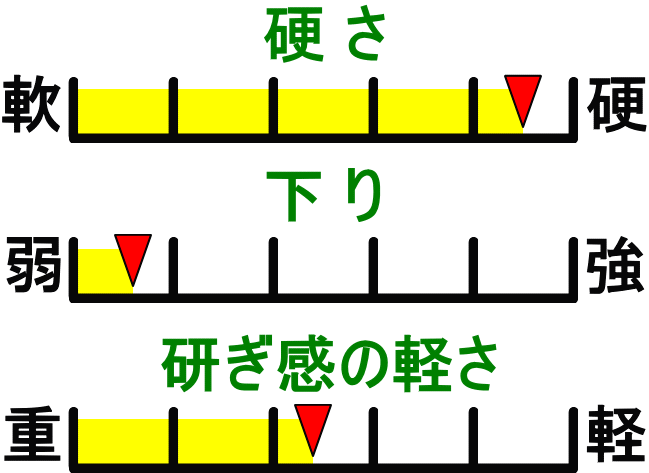
硬さ:45 下り:6 研ぎ感の軽さ:24
| しっかりと水に浸け込んで充分に吸水させてから使用するタイプ。 販売店での正式な表記は上のようにかなり長い命名となっている。 別誂えとなっているが、僕が別誂えしたのではなく販売店が製造元へ依頼して出来た製品という事と推測される。 高原料比率という事で、恐らく通常のこの手の市販品の砥石と比べると研磨剤(おそらくWAか?)の含有比率が高いのであろうと推測される。 価格は#1000としてはかなり高級砥石である。 僕の知る限り、この硬口と中硬の2タイプが販売されていた?ようである。 販売されていたというように過去形になっていますが、購入したのが2012年の11月の末頃と少し前である事と、まだその当時あった購入店のURLのサイトが見当たりませんし、ヤフオクでも店舗出品していましたが、それもざっと見たところ見つける事ができませんでしたので、ひょっとするともう販売していないのかもしれない。 |
| まだ使用頻度が低いせいか保水性能がやや不足気味である。 砥石の目が経っていない状態から研ぎはじめると、泥気は出ず水分も引いていき、鉄粉が砥石の隙間に埋まっていき白い砥石が真っ黒になっていく。 つまり目詰まりして、普通に洗っても砥面は真っ黒のままである。 このような状態になるので、ノーマルで研ぐには硬さが性能を殺してしまっている。 目を立てるか或いは名倉がわりの似たような粒度の砥石をすりあわせるか、もしくは似たような粒度のパウダーをかけて使うなどすると、砥石らしく使えるようになる。 ここまでの硬さになると砥面が崩れにくいので、砥面の平面を利用して刃物形状を直線的に矯正する等の用途にするのであれば研ぐ度に砥面を修正して常に目の立った状態で研ぐという使い方もありかもしれない。 但し硬さと目詰まりの割には下りるという感じはあるので、この辺りは高原料比率という事が作用しているのかもしれない。 |
 |
中硬に比べればやはり硬く変形しにくいようで、自発的に泥が出て高原料比率の長所である強い下りを得る事も無く、泥の無い状態では中硬に比べてやや重くつんのめる感じだが、酷い物ではない。 中硬とは硬さの差はそれほど大きくないは感じないが、大きさの特に長さでは9㎜も差がある。 焼き縮みしてこれほど縮んだのであれば、もっと硬さの差を感じても良さそうな気はする。 文字にしてしまえば9㎜程度だが、並べてみると上の画像のごとく結構な差に感じる。 同じ型枠を使用していないのだろうか?と疑問に思うほどの差に感じる。 同じような用途で研ぐとして泥のある状態で研ぐのであれば、個人的には、ニューケント硬口の感触の方が好みである。 刃を起して刃の先端だけを研ぐ小刃付けの様な研ぎでは、下り具合などの長所も出るのかもしれない。 |
刃物を研いだ時の研ぎ汁の画像

| 中硬の画像と似たような感じだが、下りが少ない分若干泥も少なめに思う。 |